 ウェーブ・シーケンスとかウェーブ・シェイプなどを音源として採用しているシンセはベクターシンセと呼ばれるのですが、いつの時代もキワモノ扱いです。
最近は大容量 PCM シンセで WAVE フォーム自体がなめらかですので、その必要性って・・・
ウェーブ・シーケンスとかウェーブ・シェイプなどを音源として採用しているシンセはベクターシンセと呼ばれるのですが、いつの時代もキワモノ扱いです。
最近は大容量 PCM シンセで WAVE フォーム自体がなめらかですので、その必要性って・・・
| |
| |
|
|
ただし、デジタルオシレーターの ROM 容量が小さな時代(1980 頃)ですから、ウェーブ自体も本当に素材的使い方しかできなく、ピアノみたいに、ハンマー音 → アタック音 → 弦の揺らぎ と波形が劇的に変わるサウンドの生成は難しく、ウェーブ素材を多く持たせるより、DX の FM のように 6 つのオペレーターのバランスをとった方が、サウンドの音色変化は豊かでした。
 そういう時代に、それならば、ウェーブサンプルを沢山入れて、その呼び出し順や音量バランスを時間軸(ベクトル)で制御してしまえと出てきた音源方式がベクトルシンセスです。ただし、ROM 容量の増加はそのまま価格に反映され、初期の PPG WAVE2.x(200 万円とか言われていましたが、当然、私の地元の楽器店では見たことがありません)、Prophet VS(98万円) 共に高価でした。
そういう時代に、それならば、ウェーブサンプルを沢山入れて、その呼び出し順や音量バランスを時間軸(ベクトル)で制御してしまえと出てきた音源方式がベクトルシンセスです。ただし、ROM 容量の増加はそのまま価格に反映され、初期の PPG WAVE2.x(200 万円とか言われていましたが、当然、私の地元の楽器店では見たことがありません)、Prophet VS(98万円) 共に高価でした。確かに、ウェーブフォーム自体が刻々と変化するのですから、サウンドはダイナミックに変化します。というより、変化し過ぎだろ!と思わせるくらい変化します。それは、ピアノなんかは生活の中にあるので違和感を感じませんが、アタックがベルでスネアの本体にノイズのリリースなんて、想像も付かないし聞き苦しいだけ・・・みたいな感じでサウンドメイクも、狙って作るよりランダムボタンを1,000回連打して偶然の産物を狙った方が精神的によろしいのがベクターシンセスです。多分、サードパーティのサウンドパッチが一番少ないのもベクターシンセで、そのくらい難しいというか使えない音しか作れません(笑)
ベクターシンセは、そういった出来上がるサウンドが使えない(笑)という弱点(?)から、あらかじめメーカーが用意したウェーブテーブルを選択していくやり方(micro WAVE 系)とサンプルを使いやすくしてシーケンスの繋ぎ目を滑らかにする独自の技術を使ったやり方(WAVESTATION)とに別れていきます。
では、Prophet VS の流れを組む、Evolver はどうなったかというと・・・オマケです(笑)というか、MIDI とシーケンスに同期させることをメインにしたベクターシンセとなっています。ある程度の操作を覚えていくうちに、果たして Evolver をベクターシンセと呼べるのか?とも思っていました。なぜなら、2 つあるアナログオシレーターの出来が素晴らしくて、デジタルオシレーターは、そのアナログオシレーターのどうしても出せない部分を補完するような使い方が私としては扱いやすいからです。
でも、考えて見れば、ウェーブフォームが MIDI テンポに同期(内部・外部選択できます)して変化していく方が、ベクターシンセという概念をブチ壊して使えるので楽しいと思っています。
具体的には、2 つのシーケンス可能なデジタルオシレーターを 4 つの 16 ステップシーケンサーでウェーブフォーム波形を 16 回変化させることができるということです。このシーケンサーは、オシレーターの周波数や、フィルター、レゾナンスなど、とにかく音符以外を割り当てるシーケンサーなんです。音程変化はオシレーターの周波数を切り替えていきます。その中の一つの機能がオシレーターのウェーブフォームのナンバーを割り当てられるということです。
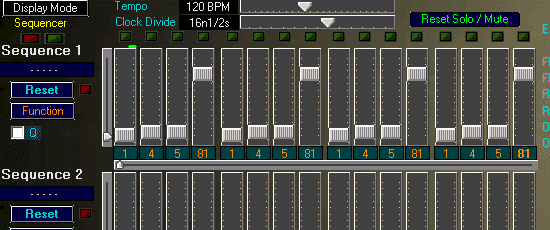
こういうシーケンサーが 4 台。パッチごとに設定できます。下図のように[ オシレーター 1 にシーケンス 3、オシレーター 2 にシーケンス 1 ] とか、[ オシレーター 3 にシーケンス 1 → 4 → 2 → 3 ]と並べて、波形変化をテンポや自律周期(可変)に同期させるような組み方もできます。

これを単に鍵盤を抑えただけのサウンドが下のサンプルです。同期をテンポにして分かりやすいように再生速度を遅くしています。
多くのことが出来すぎても手に負えなくてプリセットばかり、何もできなくて買い換える、のちょうど中間のバランスで、楽曲製作のためならシーケンサー使えば良いし、ウェーブフォーム波形をフリーハンド(Evolver も Editor ではフリーハンドできます)したけりゃ、サンプラー買えみたいな具合で、Evolver はシンセサイズの面でバランスよくまとまったオモチャです。

0 件のコメント:
コメントを投稿